通常、新商品の開発にあたっては、製品コンセプトの調査や
コンセプトテストといったいわゆる「マーケティングリサーチ」
を行います。
現在ではその手法もたくさん存在し、またユニークな方法で実施され、
消費者アンケートのようなものから、その製品コンセプトが
受け入れられるかを判断していくと思います。
当然ながら、評判が良ければそのまま商品化を進められますし、
評判が悪ければ、コンセプトを練り直すか、コンセプトそのものを
止めることになります。
しかし、製品コンセプトの調査やコンセプトテストで評判が良かった
ものでも実際には売れなかった事例や、その逆に、評判は良くなかった
が、爆発ヒットしたという歴史的な商品も多数あります。
これは、消費者のきまぐれやマーケティングリサーチの限界を示して
いるもので、特に時代の最先端を行くイノベーティブな製品・サービスに
なるほどこの傾向は強くなると言われています。
製品コンセプトの段階では、その商品が満たすニーズや商品の特徴などを
文章を中心に表現していきます。
もちろんイメージ画像を利用することもありますが、コンセプト段階で
イメージ画像を全面に出してしまうと、その印象が強すぎて、コンセプト自体が
入ってこないという事態も起こり得ます。
これは、私のコンサルティング現場でよくあることです。
商品開発会議で、まず最初にイメージ図が配られる、、、。
これが、プレゼンテーションでの戦略であるならば、まだいいのですが、
そうではなく、「言葉にしきれない思い」をイメージ図で『こんな感じ』
という雰囲気と共に伝えてしまおう(というか、「感じ取ってほしい」
という残念な思い)という考えから来ているものです。
世に有名なカリスマリーダーの商品開発初期の様々なエピソードは
今となっては、あまりにも知られ過ぎていますが、
きっと、誰もがその1シーンを真似しようとしたくなるのでしょう。
その気持ちわかります(^^
通常は、A4用紙1枚程度の中に凝縮してまとめ上げるものですが、
それを2,3筆の簡単な「絵」で表現してしまう伝説のマーケター。
「新商品のコンセプトはこれです! ジャーン♪(絵のみ)」
「おー」
みたいな言葉のないプレゼン・・確かに、かっこいい。
シンプルイズベスト的な(^^
しかし、それができるのは、悲しいかな、本当にとびぬけた能力を
もっている人のみですね。
ですので、まずは常道として、A4用紙1枚に文章を中心にそのコンセプト
をしっかりとまとめるのがスタートだと思います。
そして、「文章から実際の商品イメージを喚起させることが
どれだけ難しいことか」 という大きな壁にぶち当たるのです。
考えてみれば当然で、日常会話の中でさえ、言ったことがうまく
伝わっていなかったということが多々起こるものです。
それをただでさえ、今の世の中にない新しいモノを文章から想像
させようとしているのですから、各人の想像はバラバラになりますね。
だからこそ、テストや市場でのリサーチの意味もあるのですが。
多くの人の想像が良い創造につながることは、過去の傑作を例にとって
見ても納得できる事実です。実証済みですね。
さて、本題に戻ります。
製品コンセプトの調査には限界がある。 でした。
なぜなら、
人は文章により表現された想像物を見るまで
信用しないしそれを欲しがらないから。
すると、開発者は、我が子のようにかわいいアイディアを
どのように想像させようか、またどのようなものを想像
させようかという、想像させるイメージの統一にやっきに
なってしまいがちです。
これもよくわかります、
「そ~じゃないんだよなぁ。それじゃ〇〇と同じだよ。。。」
という気持ちから、開発者のコンセプトを100%イメージすることに
固執し始めてしまう。 調査に入る段階であれば、他者の意見を
多くもらえばもらうほど、いいはずなのに、、
コンセプトには、開発に至るまでの想いや熱意が込められている
と思います。
想いや熱意の100%伝達を心がけることは、GOOD。
そして多くの意見、反響、アンケートから
その想いを最も今の時代の消費者に求められているカタチで
具現化する。そして、早く、できる限り安く届ける。
最終的に開発者の想いや熱意が、しっかりと練りこまれている
製品というのはすばらしいですよね。
人は見るまで信用しないのであれば、
想像ではなく、実際に見たくなるコンセプト の伝達に力を入れましょう。
最終的に商品化された時におこる想像とのギャップも
とても面白いものです。
CMでもよく見ますね。
「皆様の〇〇というご要望をカタチにしたら、、、こんな
ものが出来上がっちゃいました。」 って。
そこには、いろんな戦略があるとおもいますが、
その製品も「人は見るまで信用しない、欲しがらない」
という心理をうまく応用し、おもしろい商品化を実現させた
ものなのでしょうね。







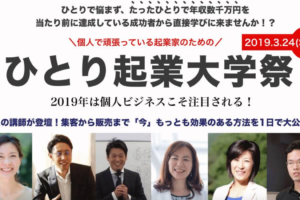

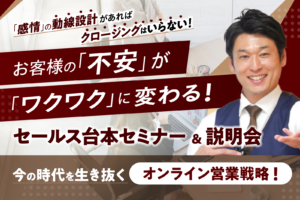

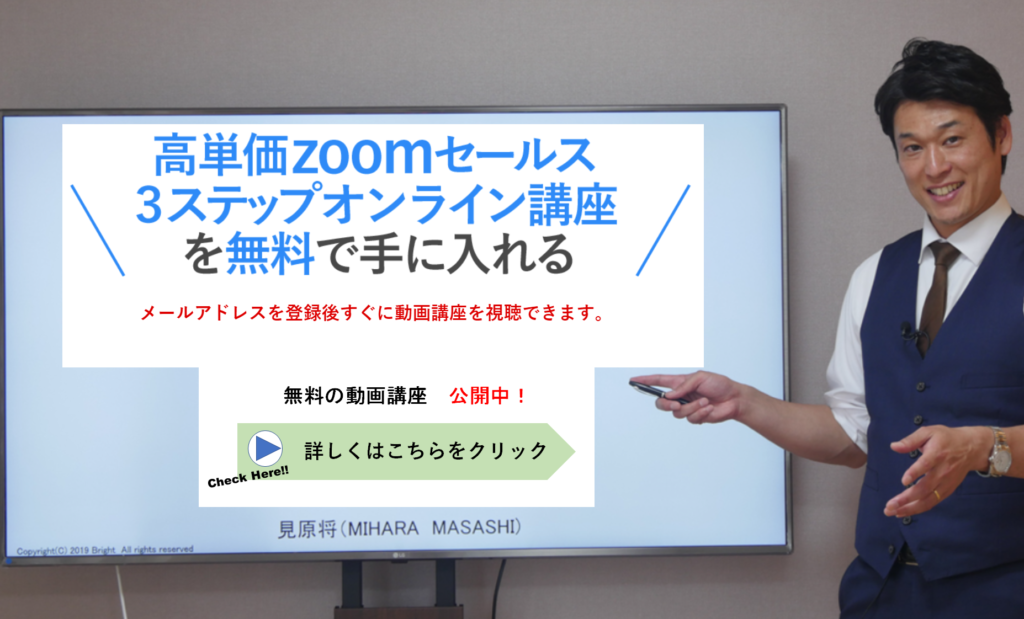

コメントを残す